経管不在による建設業許可の廃業届について

当事務所にて社会保険関連の事務代理契約をいただいているお客様のお話ですが、先日建設業許可の廃業届を行わざるを得ない事態となってしまいました。新たに許認可申請を行うのとは違い、今回の廃業届や各種書面の提出にあたっては、非常に足が重く、苦しい気持ちになりました。なぜこのようなことになってしまったのか、このような事態が生じないためにはどうすればよかったのか。今回の手続きを通じて感じたことをご紹介したいと思います。
建設業許可取得後の経緯

今回のお客様は、先代の代表取締役が役員在任中に建設業許可を取得していました。その際の建設業許可新規申請や、その後の決算変更届などは、当事務所ではなく、他の行政書士事務所が担当しておりました。お客様からも非常に信頼される行政書士の先生で、建設業許可関係の申請書綴りなどを拝見しても本当に丁寧にお仕事をされる先生だと私自身も感じておりました。
今回のお客様は、昨年に先代の代表取締役が辞任され、現在の代表取締役に代表者が交代しておりました。当事務所とのお付き合いは、現在の代表取締役となってからで、その際にも建設業許可の要件である経営業務の管理責任者の変更について確認したのですが、お客様は「建設業許可関係の手続きに関しては、許可を取得してもらった行政書士の先生にお願いしてあるので大丈夫です。」と仰っており、建設業許可取得後の手続きに関しては当事務所の受任業務ではないため、特にそれ以上お客様へ確認を求めることはありませんでした。
経管不在の事態発覚

あるとき、お客様の建設業許可通知書を見る機会がありました。当然ですが、許可通知書の名宛人は先代の代表取締役のお名前になっています。これは建設業許可取得時の通知書なので当たり前なのですが、私の頭の中に、「本当に経営業務の管理責任者の変更をしているのだろうか?」という不安がよぎりました。念のためお客様へ連絡、経営業務の管理責任者の変更の届出を本当にされているかどうか確認したところ、「行政書士の先生に確認しみてます。」とのご返答でした。

そしてすぐにお客様より当事務所宛に連絡があり、経営業務の管理責任者の変更は行っておらず、さらに現在の代表取締役は、当該法人において役員登記されてからの期間が4年間しかなく、建設業法施行規則第7条第1号イ(1)の要件を満たしていないことが判明。当該法人は1人取締役会社であり、経管不在のまま数か月が経過してしまっていたのです。
事態判明後の対応
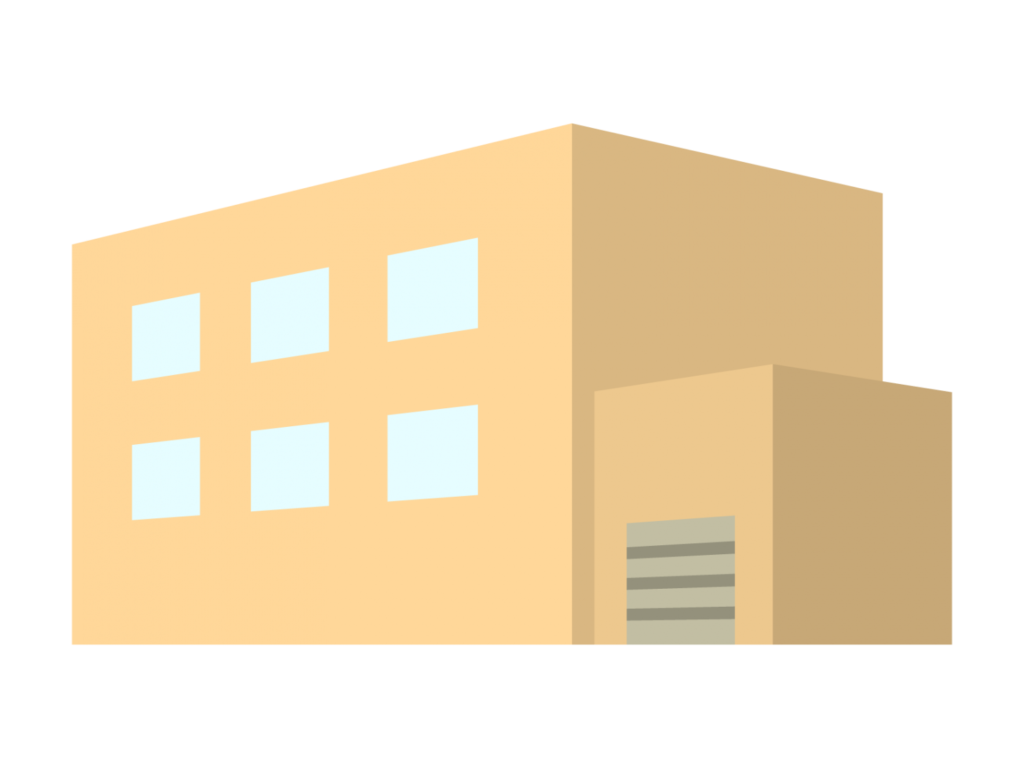
事態は急を要するため、現在の代表取締役、お客様の建設業許可や許可後の手続きを担当されていた行政書士事務所、当事務所の3者で協議した結果、お客様のご要望もあり、今後の対応について当事務所で対応させていただくこととなりました。建設業許可における経営業務の管理責任者の要件は、建設業法施行規則第7条に定められています。今回は要件の詳細解説は割愛させていただきますが、今回のお客様の場合、代表取締役ご本人に過去の役員就任履歴はなく、当該法人が取締役会設置会社ではなく、また、建設業法施行規則第1条第1号ロに定める「常勤役員等を直接に補佐する者」としての要件を満たす人員も社内に対象者はなかったため、建設業法施行規則第1条第1号イ(3)の要件を満たすことを書面で証明しなければなりません。

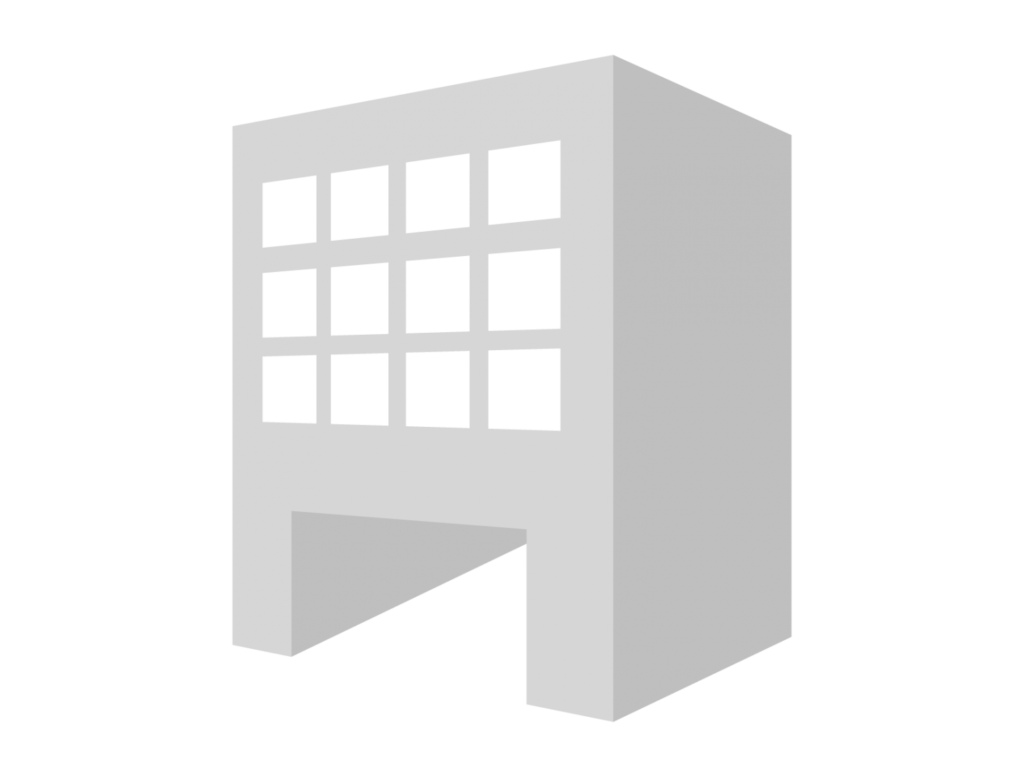
建設業において、経営業務の管理責任者や専任技術者には常勤性が求められるため、それぞれ1日でも不在の状態となれば建設業許可を維持することはできません。そのような場合には当該事由に該当した日から30日以内に廃業届を提出しなければなりません。しかし今回のお客様の場合、建設業許可要件の中でも最も重要な要件といえる「経営業務の管理責任者」が数か月にわたり不在という事態のため、すぐに県の建設業課へ状況説明を行いました。また、県内でも有数の建設業許可専門の行政書士法人にも相談し事態にあたることとなりました。
建設業課からの指摘
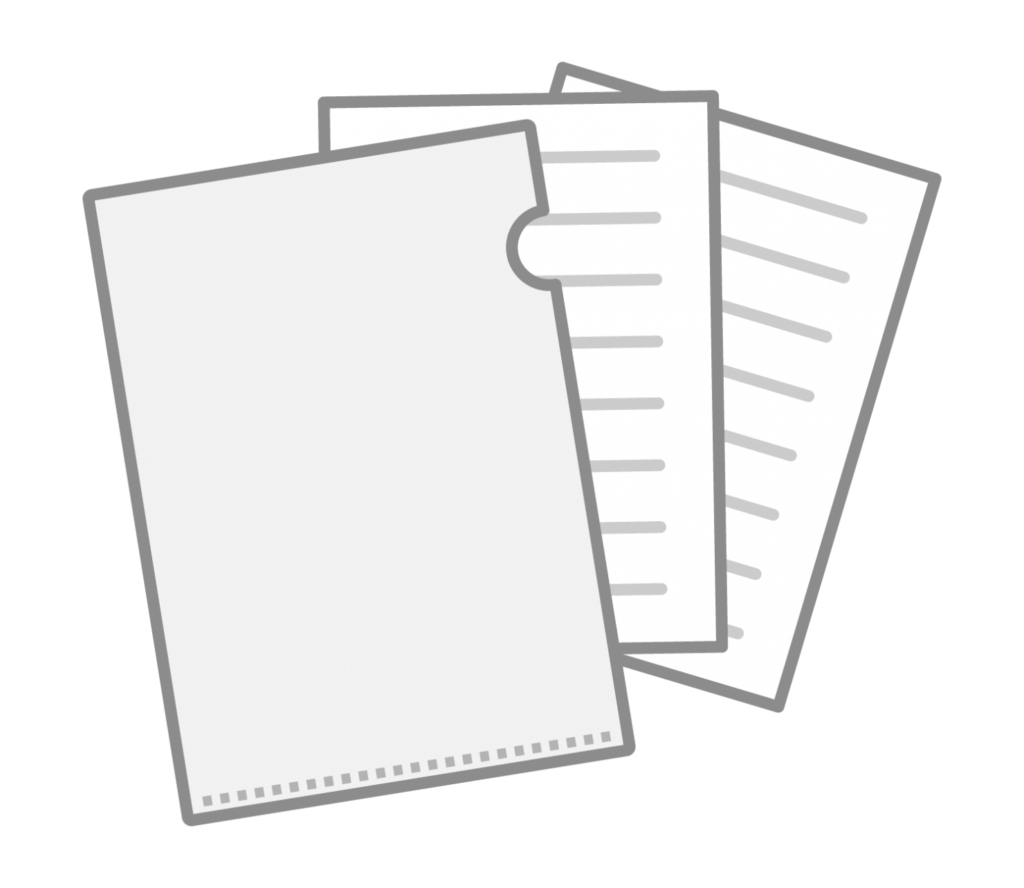
現在の代表取締役が経管としての要件を満たすことを証明できる書類の収集が可能かどうかを確認したところ、取締役就任前の会社の組織図、業務分掌規程、稟議書などはありませんでした。受注担当者名に現代表取締役の氏名の記載がある過去の注文請書等の提出が可能であることを建設業課に申し伝えたことろ、そのような注文請書では個別認定の確認書類としては認められず、早急に建設業許可の廃業届の提出と、経管の要件を満たすタイミングでの建設業許可再申請を強く求められました。県の建設業課の責任者から強く指摘されたのは、以下の点です。
| ① 受注担当者名に現代表取締役の氏名の記載がある過去の注文請書のみでは経営業務の管理責任者の補佐経験を立証する書類として受理できないこと |
| ② 許可行政庁としては、経管不在の期間が数か月に及んでいることを非常に重く捉えていること |
| ③ 建設業許可の取消処分を受ける可能性があること(※) |
| ④ 廃業届提出後の許可の取り消しは、あくまでも手続き上の取り消しとなるため、「許可行政庁による取消処分」とはならず、建設業許可の欠格要件には該当しないこと |
(※)廃業届を出さずに営業を続け、許可行政庁より建設業許可の取消処分を受けた場合は、取消処分を受けた日から5年間は建設業許可を受ける事が出来なくなります。

状況によっては、 建設業許可専門の行政書士法人に対応を引き継ぐことも視野に入れていたのですが、相談していた先生からは、「経管不在の状態がこれだけ長く続いており、確認書類の提出が難しいのであれば、経管の個別認定を許可行政庁に求め続けるのは好ましくなく、着地点としてはいったん建設業許可の取下げ(全部廃業)を行い、経管の要件を充足した時点で新規申請を行うべきであり、それがお客様の利益を最大限保護することにつながるのではないか。」とのご意見をいただきました。私も同じ考えでしたので、その旨をお客様にもお伝えすることになりました。
お客様からのお言葉

お客様には、いったん建設業許可の取下げ(全部廃業)を行い、経管の要件を充足した時点で建設業許可の新規申請を行う必要があることを伝えたところ、「経営業務の管理責任者不在の状態が続き、許可行政庁から建設業許可の取消処分を受けた場合のリスク(5年間は建設業許可を受けることができない)を考えると、そうなる前に事の重大性に気づくことができ、取消処分を回避できてよかったと考えます。自分が経管の要件を満たした時点で再度建設業許可の新規申請を行いますので、その際にはよろしくお願いいたします。」とのお言葉をいただきました。建設業許可がなくても、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事は受注が可能です。前向きな代表の言葉に、少し気持ちの重荷が取れたように思いました。
このような事態を回避するためには

建設業許可の新規申請や、許可取得後の手続きを担当してた前任の行政書士事務所の先生からすれば、「お客様から役員変更などの申出がなかったので、こちらとしては対応のしようがなかった。」と仰ることも理解できますが、建設業許可関連の手続きを一任されていた行政書士であれば、少なくとも経管や専任技術者の変更などが生じた場合、建設業許可に影響が出ること、場合によっては建設業許可の維持が困難になることをしっかりとお客様に伝える責任があったのではないでしょうか。

一般的に営業系許認可の要件は「ヒト」「モノ」「カネ」の3つに大別されます。特に公益性が高い建設業許可は、他の許認可と比較して要件のハードルが非常に高く、特にその中でも「ヒト」に関する要件が非常に複雑です。建設業許可を取得しているお客様に対して、建設業許可の要件など基礎的な部分についてもう一度丁寧にお仕えしていくことはもちろん、当事務所では毎月、建設業許可を取得しているお客様に対し、役員の変更や技術者の退職などがないかどうかの確認を実行していきます。そうすることで今回のような事態が発生することは防げると思いますので、建設業許可を取り扱う方々にはぜひ意識していただきたいと思います。

お気軽にお問い合わせください。
TEL:045-262-0214
受付時間:9:00-18:00(土曜・日曜・祝日除く)


